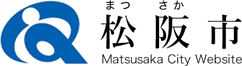本文
教育・保育給付認定について
保育園・認定こども園の認定について
教育・保育給付認定とは、子ども・子育て支援新制度へ移行する幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合に受けていただく手続きで、児童の年齢と保育の必要性の有無によって、1号、2号、3号のいずれの区分に認定され、区分により利用できる施設が異なります。
保育園・認定こども園などの利用を希望する場合は、保護者などが次のいずれかの【保育の必要性の事由】に該当し保育が必要と認められる場合に認定を受けることができます。
教育・保育給付認定申請書の内容を元に、教育・保育給付認定をし、支給認定証を交付しています。認定には期限があり、期限を延長する場合や、教育・保育給付認定申請書の内容に変更があった場合には変更申請が必要になります。認定の内容については、支給認定証をご確認ください。
保育の必要性の事由(家庭で児童を保育することができない理由)等
- 『就労』 児童の保護者などがいつも家庭の外で(月64時間以上)仕事をしているため。あるいは、いつも家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事を(月64時間以上)している。(申込時点保護者が育児休業を取得されている場合は、必ず入園月中もしくは入園月前に仕事へ復帰することが条件です。復帰しない場合や、退職した場合、入園内定を取消しする場合があります。)
- 『妊娠・出産』 母が出産の前後である。(入園できるのは、最大で出産予定月の前2か月と出産(予定)日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間となります。)
【例】令和4年4月30日が出産日から起算して8週間を経過する日に当たる場合、5月末日で退園となります。 - 『疾病・障がい』 児童の保護者などが疾病または心身に障がいがある。
- 『介護・看護』 児童の同居親族(長期間入院等をしている親族を含む)に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいて、保護者などがいつもその看護にあたっている。
- 『災害復旧』 住家が火災や風水害や地震などの災害にあい、保護者などがその復旧にあたっている。
- 『求職活動』 児童の保護者などが求職活動(または起業の準備)を継続的に行っているため。(※入園後1か月以内に月64時間以上の仕事に就労開始することが条件です。また、同一年度内に同一保護者による二度目の求職活動の事由への変更は、認められません。)
- 『就学』 児童の保護者などが(学校教育法等における学校等※職業訓練を含む)就学している。(就学が決まっている場合、入園後1か月以内に就学開始することが条件で申込みができます。)
- 『育児休業』 育児休業取得時にすでに、保育園・認定こども園を利用していて継続して利用することが必要と認められる場合。
- 『虐待やDVのおそれがあるため』 虐待やDVのおそれがある場合。
- 『その他』 1~9の要件に類する状態にあり、市長が認める場合。
支給認定証の見方
支給認定区分
|
教育・保育給付 |
対象年齢 |
保育の必要性 |
利用できる施設 |
|---|---|---|---|
| 1号認定 | 満3歳以上 | なし | 幼稚園 認定こども園 |
| 2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育園 認定こども園 |
|
3号認定 |
0~2歳 あり |
あり |
保育園 認定こども園 小規模保育事業施設 |
保育必要量区分
(標準・短)時間のいずれか記載
保育の必要性の事由
保育希望理由は、保護者の保育の必要性の理由が父と母で異なる場合、入園期間が短くなる事由が表記されます。
支給認定期間
認定の有効期間です。2号、3号認定の場合、保育の必要性の事由によって異なります。
3号認定は、最長で満3歳の誕生日の前々日になります。
保育標準時間・保育短時間の区分について
2号、3号認定の保育(標準・短)時間の区分は、保育の必要性の事由によって異なります。※父母のいずれか一方が保育標準時間に該当しても、他方が保育短時間に該当する場合、児童の保育必要量は保育短時間となります。
| 保育必要量 | 保育の必要性の事由 |
|---|---|
| 保育標準時間 (7時00分~18時00分) |
『就労』『就学』『介護・看護』で要する時間が月120時間以上 『妊娠・出産』『保護者の疾病・障がい』『災害復旧』など |
|
保育短時間 |
『就労』『就学』『介護・看護』で要する時間が月64時間以上120時間未満 |
※開園時間が7時00分からの保育園と7時30分からの保育園があります。令和5年度入園案内33ページ、34ページを参照ください。
※保育の必要性の事由が『就労』事由で保育短時間認定に該当するが、通勤時間が長い等の理由のある方については、別途申立書により申し出てください。保育標準時間認定を認められる場合があります。
入園後の手続きについて
申請いただいた内容に変更があった場、教育・保育給付認定を再審査する必要がありますので、必ず変更を希望する月の前月までに、こども未来課または各地域振興局地域住民課で、教育・保育給付認定の変更申請を行ってください。
教育・保育給付認定申請書は原則保護者が記入・提出いただき、以下の書類を添付してください。
教育・保育給付認定に必要な添付書類は、保育の必要性の事由によって異なります。下記(2)-1参照
(1)手続きが不要な変更(児童の年齢による区分による変更)
教育・保育給付認定は、保育を必要とする児童の年齢により、3号認定(0~2歳)と2号認定(満3歳以上)に分かれています。
3号認定の有効期限は、満3歳に達する日の2日前です。満3歳になる1日前から、2号認定へ変更されます。
⇒変更に係る申請の必要はなく、こども未来課から変更した支給認定証を交付します。
(2)-1手続きが必要な変更(保育の必要性の事由や、事由の期間、就労時間などが変わった場合)
就労先が変わったとき、退職したとき、育児休業を取得したときなど、保育の必要性の事由が変わる場合や、申請した時と状況が変わった場合は届け出が必要です。
| 状況が変わった場合の例 | 申請に必要な書類 | 変更後の事由 | 認定期間 |
|---|---|---|---|
|
新たに就労 |
家庭外勤務…事業主が証明をした『就労証明書』 |
就労 | 就学前まで |
|
自営業・農業(個人事業主)…『就労証明書』+『自営業申告書』+『自営の証明書類の写し』(確定申告書、開業届、農家基本台帳等) ※電子で申告した方は、ご自身で印刷して提出してください。確定申告書を提出する場合、就労先の名称、業種等が記載されているか確認してください。必要に応じて、収支内訳書・青色申告決算書等の追加書類の提出を求める場合があります。 |
|||
| 自営業(専従者)…『就労証明書』+『自営業申告書』+『専従者であることを証明できる書類の写し』(事業主の確定申告書、源泉徴収票等) | |||
|
産休・育休後に復職するとき |
事業主が証明した『育児休業復帰証明書』 ※休暇前と就業時間や就業場所が変更になる場合は、復帰後の内容を証明をした『就労証明書』 |
就労 | 就学前まで |
|
退職して求職活動をするとき |
『確約書』 ※入園後1か月以内に月64時間以上の仕事に就労開始することが条件です |
求職活動 | 3か月 |
|
病気にかかり療養するとき |
医師が記入した『意見書』 ※障がいの場合
|
疾病・障がい |
治癒見込み期間 による |
|
出産後 |
事業主が証明した 『育児休業期間証明書』 |
育児休業 |
就学前まで |
|
児童の同居親族等の介護をするとき |
『家庭状況申告書』 | 介護・看護 | 就学前まで |
|
出産予定があるとき(退職する場合) |
1.『母子健康手帳の写し(表紙及び 分娩予定日の記載があるページなど)』 ※『分娩予定日証明書』・『産科医療 補償制度登録証』等でも可 |
妊娠・出産 | 出産予定月の前2か月間と出産(予定)日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
|
学校に通うとき(職業訓練を含む) |
|
就学 | 保護者の就学期間 |
保育を必要とする事由がなくなったときは、退園の手続が必要です。
※正当な理由なく変更の手続を行わないとき、又は保育を必要とする事由に該当しなくなっていたときは、子ども・子育て支援法第24条により、認定を取り消す(退園になる)場合があります。※
教育・保育給付認定の保育の必要性の事由の変更について、以下の事由変更はできません。
(例) 「妊娠・出産」⇔「求職活動」、「求職活動」⇒「疾病・障害」、「求職活動」⇒「介護・看護」、「育児休業」⇒「介護・看護」、同一年度内の同一保護者による二度目の「求職活動」の事由への変更は認められません。
※次の変更については認められる場合があるので、こども未来課へ相談ください。
「疾病・障害」⇒「育児休業」、「介護・看護」⇒「育児休業」、「災害復旧」⇒「育児休業」、「育児休業」⇒自己都合による「求職活動」
(2)-2手続きが必要な変更(世帯状況や申請内容が変わったときなど)
申請している世帯の状況(同居の人か増えた・減ったなど)が変わった場合や引っ越しにより住所が変わった場合など申請内容が変わったとき申請が必要です。市役所・各地域振興局で教育・保育給付認定申請書を記入してください。
| 状況が変わったときの例 | 申請が必要な書類 |
|---|---|
|
2号→1号認定へ変更 |
教育・保育給付認定申請書 |
|
1号→2号認定へ変更 |
教育・保育給付認定申請書 保育の必要性の事由に合わせた書類 |
|
ひとり親になった(※) |
教育・保育給付認定申請書 申立書 |
|
ひとり親だったが結婚した(※) |
教育・保育給付認定申請書 申立書 結婚相手の保育の必要性の事由に合わせた書類 |
|
祖父母と同居・別居となった(※) |
教育・保育給付認定申請書 |
|
障がい者(児)と同居となった(※) |
教育・保育給付認定申請書 次のいずれかの書類(写し)
|
|
同居者に身体障害者手帳等が交付となった(※) |
教育・保育給付認定申請書 次のいずれかの書類(写し)
|
|
保護者代表を変更する(保護者代表が市外へ転出等) |
教育・保育給付認定申請書 |
|
支給認定証の再発行 |
支給認定証再交付申請書 |
|
市内で引越しをする(同居者の増減を含む)(※) |
教育・保育給付認定申請書 |
|
市外へ転出をする |
在園児:退園届 申込中:取下願 |
※保育料・副食費が変更になる場合がありますので、すみやかに申請手続きしてください。
申請が必要かどうか迷われる場合は、
こども未来課(0598-53-4083)へお問い合わせください。
ダウンロードファイル(※各種申請書について、下記ファイルを印刷いただき使用いただけます。)
- 就労証明書[PDFファイル/128KB] [Excelファイル/55KB](令和6年9月から新様式に変更しております。)
- 自営業申告書[PDFファイル/163KB][Excelファイル/27KB]
- 意見書[PDFファイル/127KB][Excelファイル/17KB](令和5年9月から新様式に変更しております。)
- 家庭状況申告書家庭状況申告書 [PDFファイル/169KB][Excelファイル/35KB](令和5年9月から新様式に変更しております。)
- 確約書 [PDFファイル/230KB] [Wordファイル/41KB]
- 申立書[PDFファイル/120KB][Wordファイル/35KB]
- 育児休業期間証明書 [PDFファイル/137KB] [Wordファイル/19KB]
- 育児休業復帰証明書 [PDFファイル/179KB] [Wordファイル/20KB]