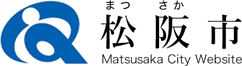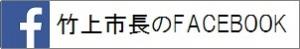本文
市長定例記者会見 発言要旨(令和7年2月25日)
所感
まずは議会が始まりまして、3月19日までだったかな。長丁場になりますが 頑張っていきたいと思います。
あと、昨日ですかね。ウクライナの戦争が始まって丸3年というふうなことで、様々なニュース等々で取り上げられていました。私も日曜日に、某局のスペシャルがあって。女性兵士を追うって。あれは1時間番組ですかね。それを見て、女性は志願兵なんですね、すべてね。ものすごく大変というのが見てて思いました。3年というのは当事国に立つとこんなに大変なことかなと、改めて早く平和が 訪れることを祈りたいと思います。
最近の話題で、非常に全国の自治体で物議をかもしている話があって。全国を300か400の市でいいと。言ってみれば昔の話ですよね。廃藩置県というのがございましたけど。それは一時道州制の議論の時もありましたし、当時、地方制度調査会でもそういう話が言われたことがございました。全国を300市にして、中間の広域自治体の県をなくしてしまえというふうな議論があって。最近は大臣がそういう発言をされたということで、自治会の方がかなり反発をされているというふうなことかと思います。
これはね、国のことに関してあまり私がどうこういう立場ではないといつも申し上げております。ただ感想として申し上げますと、ついこの間、合併20周年式典とかね。今年はそういう記念イヤーなので。20年経ってさえですね、なかなか合併の感覚と言いますか、一つの市になって、町になって、町づくりというふうなところがようやく20年目にして、ある程度市民の皆さんにご理解得られるようになってきたのが私の感覚です。
確かに合理的に考えればその方がいいのかもわかりませんけども、現実そんな簡単には。今全国の基礎自治体が1700ですね。それを300、400に合併をしていくというのは至難の業でして。それは今からちょうど20年前、平成の大合併ですよね。あの時いろんな市町村が合併協議をやって、破談になったところもたくさんございます。ついこの間、防災協定を結んだ大垣市という町は松阪市と非常に似通っています。例えば人口規模がほぼ一緒、市民病院があって、さらには競輪場がある。そういう意味ではかなり似通っているんですけど、違うところが一つ。面積と市の位置です。単純に言いますと、飛び地が二つあるんです。当時の合併協議の中で抜けていった。本当はもっと大きい市になる予定が抜けちゃった。で、この大垣市は飛び地が二つできた。だいたいそういう話でして。そこは市政の運営的には結構大変みたいな話をこの間、協定のあと懇談する場がありましたので、そんな話を伺いました。何を言いたいかというと、なかなか足し算引き算でこういう発表ができるかというと、なかなかそういうものでもないというふうなところで、これは難しい話だなというふうに私としては感じております。
それからですね、年初に人口の話をいたしました。ある程度詳しいことがわかってきましたので、そこについて報告をしておこうと思います。当時は出生数、それから亡くなった人の数、それでもってというような話をさせていただいたかと思っております。
結局1月1日現在で、令和5年、6年の話ですね。人口減少は1290人です。 これは確定値です。あの時お話させていただいた、あれも速報値で言いましたけど、ほぼだいたい一緒だったんですかね。死亡数の確定値は2178人で、出生数が844人です。だから差し引くと1304人ということになります。で、一年間の人口減少が1290人です。要するに14人違います。
人口は2通りあると言いましたけども、自然減ですね。いわゆる産まれる亡くなる、この差が自然減。今どこの自治体もこの現象、東京以外はほぼ一緒。亡くなる方よりも産まれる赤ちゃんの方がずっと少ない。これで1300自然減になる。けれども人口減少は一年間で1290人は社会的増減で14人増えた、そういうことになりますね。
で、何が言いたいかというと、実は市長になって10年目で初めてのことなんです。地方都市松阪市は、いわゆる社会的移動でマイナスになる市でございまして。高校卒業してから進学する子どもたちですね。通えるところの子どもたちが非常に少ない。要するに卒業した半分の学生が県外に出ていくわけですよ。それがいわゆる社会減を招いている。ある意味でね。じゃあどうして今年、社会減がプラスになったのかと言いますと、これが結論的にいうとあまりよくわからないけれども、日本人の社会動態による減少が少なくなったというのがだいたいの分析結果で。外国の方はだいたい一定数増えていくわけです。あまりここのところ変わってないです、増えていっている数がね。極端に去年と今年で言いますと、ここの社会増減のところが300人以上減ったのが、それがプラスに転じた。 ここが大きく違いまして。日本人の社会動態の減少がかなり少なくなった。
じゃあ、どの世代なのというようなところを一度見てみたんですけどね。そうすると20人以上の増えたところを言いますと19歳、それから21歳、22歳、23歳、それから26歳、27歳、31歳、32歳。ここらへんが20人以上プラスになっている世代なんです。
まず一つには、就職で松阪に来てくれた方がそれなりに増えてきたというのがここらへんの、19~23ぐらいまではそれが言えるかなというのが一つ。それから26、27。いわゆる転職したパターンはあるのかなと。それから31、32もよく似た話です。例えばいろんな人生の中のイベントがございます。結婚するとかね、お子さんができるであるとか、いろいろイベントがございます。その節目で帰ってきたのかもしれない。ここはわからないです、正直。ただ20人以上で増えているというのは、こういう世代の方がプラスの方に転じてもらっているということを考えていくと、今やっている、いわゆる若者定住施策の、例えば子育てしやすい街であるとかね。企業誘致であるとか、そういったところは今のところです。これはまだそんなに簡単に成功するとまでは言えないけど、方向的にはそう間違っていないかなと。私的には、今年の人口の分析をしてみると、そういうことが言えるかなということで思っております。
ただ、やっぱりここに住んでいる若者たち。外国人の方も一定程度増えてますから、毎年。そう考えると、住人という数字はまだまだ、ここに住んだ若者が全部ここに戻ってくるとか、そういうものではもちろんないので。それはね、人の生き方だから。我々が斟酌する話ではないけども、ある一定程度の若者たちが戻ってきてくれているというのが実態ではなかろうかというところで、私的には良い結果になっているなと。一年限りの話でどうのこうのいう話ではございません。傾向的にはあるかなというふうなことを思いました。
発表事項
- 【契約DX】令和7年4月から一般競争入札等における電子契約の本格運用を開始します!
- 令和7年度人事異動発表を変更します
- 「松阪市役所のパーパス」策定のための職員アンケートの結果について
- 「松阪市総合計画~和で結びみんなで築く松阪市~」が完成しました
資料
00.市長記者会見事項書_R7.2.25 [PDFファイル/173KB]
01-1.【契約DX】令和7年4月から一般競争入札等における電子契約の本格運用を開始します! [PDFファイル/481KB]
02.令和7年度人事異動発表を変更します [PDFファイル/161KB]
03.【松阪市役所のパーパス】策定のための職員アンケートの結果について [PDFファイル/421KB]
04-1.「松阪市総合計画~和で結び みんなで築く 松阪市~」が完成しました [PDFファイル/239KB]