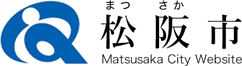本文
入札システムのご案内(工事等)
発注の公告から落札まで
松阪市では、建設工事、測量・建設コンサルタント等の委託の入札において、入札参加希望者の受注意欲を尊重する「条件付き一般競争入札」を採用しています。
この入札方法は、入札参加を希望する方で、入札参加資格条件を満たしている方はすべて入札に参加できるものです。
入札参加を希望される場合は、下記事項及び「入札心得」を確認のうえ参加申請を行って下さい。
発注の公告
毎週月曜日の午後3時頃、ホームページ(入札の広場)の「工事等発注の掲示板」へ掲示します。(月曜日が休日の場合は、原則として前週の金曜日。公告日から入札(開札)日の間に休日が含まれる場合は、入札参加申期間等を調整する場合があります。)
設計図書は発注公告に添付するデータで確認してください。(データ添付が困難な場合は、紙による閲覧を実施する場合があります。発注公告にその旨を記載しますので確認してください。)
発注公告文を確認の上、入札参加資格条件を満たしていれば参加申請できます。
入札の参加申請
電子入札案件の入札に参加しようとする方は、電子入札システム中の入札情報システム(市が発注する入札案件情報、開札結果等を電子的に公開するシステム。)により入札予定の工事名、工事概要、入札参加資格要件、入札及び開札の日時等を確認し、指定された日時までに電子入札システムにより競争参加資格確認申請書を添付し入札参加申請を行ってください。郵便入札の場合は、発注公告から提出書類を確認し、Faxにて参加申請を行ってください。
また、いずれの場合も共同企業体を構成して参加申請する場合は、参加申請関連書類を契約監理課まで直接提出して下さい。
登録の有効期間
建設工事の場合は直近の経営規模等評価結果通知書の審査基準日から1年7ヶ月の有効期間を経過している場合は、入札に参加することができません。
最新の経営規模等評価結果通知書が届きましたら速やかに、三重県建設技術センター 入札参加資格登録共同受付担当(〒514-0002 三重県津市島崎町56番地)へご提出ください。
入札参加者の所在区分
発注公告で所在区分が条件指定された場合は、次の区分により判断して下さい。
| 区 分 | 定 義 |
|---|---|
| 市内業者 | 松阪市内に本店を有する業者で、市税を完納している業者 |
| 準市内業者 | 松阪市内に建設業の許可を受けた支店または営業所を有し、その支店または営業所に契約権限が委任されている業者(市内の支店または営業所で契約が可能)で、市税を完納している業者 |
| 測量・建設コンサルタント等の業者は、松阪市内に登記された支店または営業所を有し、その支店または営業所に契約権限が委任され、市税を完納している業者 | |
| 県内業者 | 三重県内に本店(社)または建設業の許可を受けた支店・営業所を有し、その支店・営業所に契約権限が委任された業者 |
| 測量・建設コンサルタント等の業者は、三重県内に本店(社)または支店・営業所を有し、その支店・営業所に契約権限が委任された業者 | |
| 県外業者 | 上記以外の登録業者 |
※準市内業者:入札・契約関係規則等 >松阪市市内業者及び準市内業者の認定基準要領
組織図、案内図及び写真の提出について
準市内業者の方は、「組織図、案内図及び写真」及び「公共料金納付状況報告書」等の提出が必要です。提出が無いと入札に参加できませんので必ず提出して下さい。
※提出書類:準市内業者の提出書類
工事履行実績の確認(平成31年4月1日改正)
同種工事の判断
原則、建設業法における29業種で判断しますが、次の工事については、別に判断します。
(1)下水道推進工事=下水道推進工事
(2)給水工事=水道管布設工事
(3)林道開設・復旧工事=林道開設・復旧工事、道路改良工事または地すべり・砂防工事
(4)審査会決定案件については、それによるものとします。
同規模工事の判断
(1)発注案件における設計金額(消費税込み)の50%を下限に、履行実績の契約金額で判断します。
(2)審査会決定案件については、それによるものとします
実績とする対象
・履行実績は原則として、発注年度及び過去15 年度において完成したものを対象とします。
※工事履行実績の確認運用基準:入札・契約関係規則等>工事履行実績の確認運用基準
また、入札参加申請時に必要となる「工事履行実績の確認資料(コリンズ・契約書の写し等)または技術者の資格証等」については、電子入札システムで提出してください。
入札参加者の決定
資格審査のうえ参加資格が無い業者には、電子入札案件は、電子入札システムにより参加否認を行い、郵便入札案件は指定期日までに電話で連絡します。指定期日までに参加否認または連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとします。
質問書
質問書の受付・回答は原則としてFaxで行います。
質問書は指定書式を使用し、Fax番号を記載して下さい。
※質問書:入札・契約関係書類ダウンロード>設計図書等に関する質問書
入札方法
電子入札の場合は、「競争入札参加資格確認通知書」の受信後、指定された期日までに発注公告の記載にしたがって入札書等を送信してください。
郵便入札の場合は入札・契約関係書類ダウンロードから必要な書類をダウンロードし、送付して下さい。
宛先は「松阪郵便局留」です。
封筒は、1件の入札につき1枚です。(入札回数は1回のみ)
入札書を封筒に2枚以上入れた場合や封筒表紙の件名と同封された入札書の件名が異なる場合等は「無効」になります。
郵送方法は、郵便局の窓口で「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかで行い、開札終了まで差出控えを保管してください。
発注公告で指定する到着期限(松阪郵便局に届く期限)を過ぎると入札には参加できません。
郵便入札用の封筒について
入札書を郵送する封筒は、本市の指定サイズ【一般的に長3封筒(長三、長形3号)と同じサイズ】の封筒を使用して下さい。販売はしません。 市指定サイズはこちら
封筒及び入札書は、次のことに注意のうえ作成して下さい。
(1)入札書に記入する入札金額の先頭に「¥」を付け加えること。
(2)入札書の工事(目的)名及び工事(施行)場所は、正確に記入すること。
(3)入札書の日付は、開札日を記入すること。
(4)入札書のあて先は、各公告の発注者をよく確認(市長または上下水道事業管理者等)のうえ記入すること。
(5)入札者の印鑑は、必ず登録の使用印鑑(登録された印鑑)で押印すること。
(6)入札書は、1件につき、1枚限りです。封筒に入札書が2枚以上入っていた場合や、封筒表紙の件名と同封された入札書の件名が異なる場合は「無効」となります。
(7)入札書を入れる封筒には、「開札日」、「件名」、「差出人」及び「入札書在中」を必ず記入すること。
(8)郵送方法は、「一般書留」、「簡易書留」及び「特定記録郵便」のいずれかにより差出が確認できること。
(9)封筒は、必ずのりで封書すること。(セロハンテープ類によることは禁じます。)
入札(開札)日について
入札(開札)日は、原則木曜日としています。(木曜日が休日の場合は翌開庁日などに調整します。)案件ごと確認ください。
開札の立会い
入札参加資格審査を通過した者に入札参加申請書到着順の番号を付し、参加者数に応じて次の表右欄に掲げる番号に該当した方2名を立会人として選定し、開札に立ち会っていただきます。
ただし、電子入札案件は原則として立会人を選定しません。(平成31年4月1日以降の公告分から試行)
立会人の選定は次の方法により行ないます。
| 資格審査を通過した参加者数 | 立会人となる番号 |
|---|---|
| 2以下 | すべて |
| 3~5 | 2・3 |
| 6~10 | 3・6 |
| 11~15 | 4・7 |
| 16~20 | 6・11 |
| 21~30 | 9・17 |
| 31以上 | 13・25 |
設計価格の事前公表について
原則として、設計価格を発注公告に掲示します。
予定価格の算出
設計価格事前公表型の入札における予定価格は、設計価格と同額とします。(令和3年4月1日改正)
最低制限価格(令和5年3月1日改正)
最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額とする。以下 同じ。)の算出の基礎となったそれぞれの費目の金額に対し、下記の最低制限価格算定基準に 記載の業種区分によるそれぞれの率を乗じて得た1から4の合計額(千円未満切り捨て)とする。 ただし、その算定額が予定価格に別記の最低制限価格の範囲に定める上限の率を乗じた金額 (千円未満切り捨て、以下「上限額」という。)と下限の率を乗じた金額(千円未満切り上げ、 以下「下限額」という。)の範囲外となった場合は、範囲を超える場合においては上限額を、範囲を下回った場合においては下限額を最低制限価格とする。
最低制限価格算出方法について(令和5年6月5日以降の公告にかかるものから適用)
積算内訳書の入札時提出について
すべての建設工事(除草及び植栽管理等の維持業務委託、測量・建設コンサルタント等の委託は除く。)の入札について、入札書提出時に積算内訳書を提出いただきます。電子入札では入札書に添付、郵便入札では入札書に同封します。提出要領等はそれぞれの発注公告でご確認ください。
入札書に積算内訳書の添付(同封)がない場合や積算内訳書の内容に不備があると入札書が無効となる場合がありますのでご注意ください。
入札結果
入札結果は、開札当日に入札情報システム、ホームページにて公表します。
同日落札制限
同日に開札する契約金額4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)の工事は、原則落札件数を1業者1件とします。(令和7年2月1日改正)
従って、開札順により受注希望の高い工事に参加できなくなる場合もありますのでご注意下さい。(開札順は金額・業種を問わずランダムに設定します。)なお、同価入札の場合、開札後、電子くじにて落札者(落札候補者)を決定しますので、その後の開札に入札参加されていた場合は無効扱いとなります。
*委託(測量・建設コンサルタント等)は、金額にかかわらず適用します。(平成18年9月1日改正)
契約時における添付書類について
落札者との契約締結には、次の書類(完納証明書等)の添付を義務付けます。
| 落札業者 | 提出書類 |
|---|---|
| 市内、準市内業者 | 市税、県税及び国税の完納を証明する書類の写し |
| 県内業者 | 県税及び国税の完納を証明する書類の写し |
| 県外業者 | 国税の完納を証明する書類の写し |
注)上記証明書は、発行日から3ヶ月間を有効期間とします。
契約保証金
契約者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、設計金額500万円未満の工事契約(委託を含む。)で、事前に履行証明書等の提出がある場合は免除となる場合があります。
設計書内訳の公表
開札後に設計価格の内訳を公表します。
- 公表の対象
すべての建設工事(随意契約を除く)
- 公表の内容
土木工事は「設計内訳書」、建築工事等は「工事費内訳書」
- 公表の場所及び方法
「設計内訳書」等の写しを契約監理課閲覧カウンターで公表
- 公表の時期と期間
原則、契約締結日(開札日の翌週火曜日)から公表します。公表期間はこの年度中とします。
なお、開札日から翌週火曜日までに休日があるとき等、公表日が遅れる場合があります。
(平成27年4月1日改正)
その他
開札は、次の事項を遵守することを原則として公開します。
- 開札場内での私語、雑談、携帯電話等の使用は禁止します。
- その他開札執行を妨げる行為等をした者は退場とします。
なお、上記事項は入札及び契約に関する要領等の概略を記載したものですので、詳しくは入札・契約規則等のページからご確認下さい。