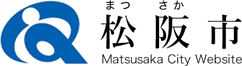本文
排水設備工事の手続きについて
排水設備工事について
公共下水道へ接続する排水設備工事を行う場合は、松阪市上下水道事業管理者へ申請手続きが必要になります。
手続きをせずに排水設備工事を行った場合は、工事の申請者や工事をした工事店への罰則が適用されます。
排水設備指定工事店の皆さんへ
排水設備の手続き方法と指定工事店の責務と遵守事項等を確認し手続き漏れのないよう徹底してください。
申請者の皆さんへ
排水設備工事は松阪市の指定工事店に依頼してください。工事完成後2週間を経過しても排水設備工事の検査日の連絡が工事店からない場合は、下水道建設課 生活排水係(Tel 0598-53-4132)までご連絡をお願いします。
排水設備の計画確認申請が必要な場合とは?
- 新規で排水設備を設置する場合。
- 浄化槽や汲取トイレからの切替え
- 新築、増築等による接続
- 建替で排水設備工事のやり直しや追加をする場合。
- リフォームで排水設備工事のやり直しや追加をする場合。
排水設備工事の範囲とは?
新築、増改築などで、便器、洗面ボウルなどの衛生器具、トラップ、阻集器、排水槽、除害施設とこれらから出る汚水を受ける排水管を含めた排水設備の工事を行う場合は申請手続きが必要となります。
ただし、軽微な工事や排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事については、申請を省略できます。
軽微な工事等とは?
- ますのふたの取替え。
- トラップ(防臭装置)、ストレーナー(ごみよけ装置)等の取替えで確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微なもの。
- 確認を受けた時点の機能と変わらない衛生器具等の取替え等。
※衛生器具の取替えにより機能が変わる場合は申請が必要です。
排水設備工事を行うには?
- 排水設備工事は市の指定を受けた工事店でなければ行えません。
- 排水設備工事を行おうとする者は、事前に上下水道事業管理者の確認を受けなければなりません。
- 排水設備工事の完了届は、工事が完了した日から7日以内に届出なければなりません。
このほかにも項目がありますので、詳しくは条例の抜粋をご覧ください。
公共下水道条例(抜粋)
※全文はホームページの例規集に掲載しています。
指定工事店の責務及び遵守事項
第11条 指定工事店は、下水道に関する法令並びにこの条例及び管理者が定めるところに従うとともに、次に掲げる事項を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
(1) 排水設備工事の施工の依頼を受けたときは、正当な理由が無い限りこれを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。
(5) 工事は、第5条に規定する排水設備等の計画の確認を受けた後でなければ着手してはならない。
(6) 設計及び施工は、責任技術者の監理の下において実施しなければならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失により生じた場合を除き、無償で補修しなければならない。
(8) 第14条に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められたときは、速やかに改善し、又は補修し、再度検査を受けなければならない。
(9) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
指定の取消し又は一時停止
第13条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(5) 不正な手段により第6条第2項の指定を受けたとき。
2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定により指定の効力の停止があった場合においては、当該停止の期間は、第6条第3項の有効期間に算入する。
4 第1項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止により、指定工事店に生じた損害については、市はその責めを負わない。
排水設備指定工事店の指定
第6条 排水設備等の新設等の次の各号に掲げる工事を除き、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(1) 市が実施する工事
(2) 規程で定める軽微な工事
(3) 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定工事店以外の者が行うことが適当なものとして規程で定める工事
(4) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事
2 指定工事店の指定を受けようとする者は、管理者の指定を受けなければならない。
3 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して4年とする。ただし、管理者が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
4 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、更新手続きをし、再度指定を受けなければならない。
指定工事店の指定の基準(※基準を満たさなければ指定取消になります。)
第8条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
(1) 三重県内に営業所がある者であること。
(2) 財団法人三重県下水道公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証の交付を受けている者(以下「責任技術者」という。)を選任していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ 法人であって、その役員のうちアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
2 管理者は、第6条第2項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
排水設備等の工事の検査について
第14条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が命じた職員の検査を受けなければならない。
責任技術者の職務等について
第9条
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第14条に規定する検査の立会い
3 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
5 責任技術者は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することができない。
公共下水道の使用時おける、除害施設の設置等について
第15条 法第12条第1項の規定により、次に掲げる基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満