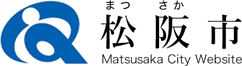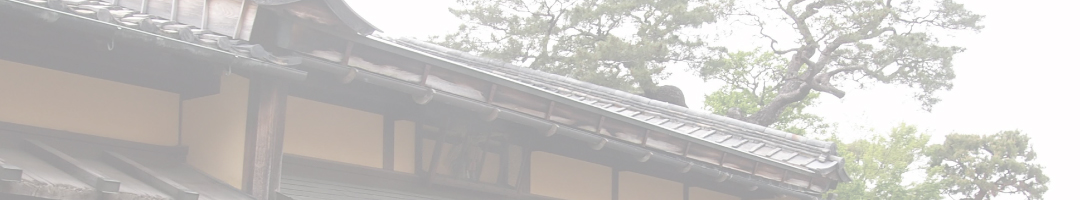ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
三井家発祥地
本庁管内 市街地区
23-60
三井家発祥地
(みついけはっしょうち)
市指定史跡
概要
江戸時代/本町/指定面積:568.49m²/昭和31年7月3日
江戸時代屈指の豪商であった三井家は、松阪本町から、やがて「江戸店持京商人(えどだなもちきょうあきんど)」となって天下に飛躍していった。この三井家発祥地はその父祖の記念の地であり、記念碑が建てられている。
創業の祖(家祖)は高利(たかとし)(1622~94)であるが、ここには高利の祖父高安と父高俊の墓碑、高利の長兄らの供養碑ととも高利の産湯(うぶゆ)に使ったという伝承のある井戸がある。
三井家は父高俊の代に松阪に居宅を構え、この発祥地周辺に広い地歩を占めていた。しかし、本格的な江戸進出を果たした高利は、京都に居宅を移す一方、松阪には同族と松阪店を置き、紀州藩の御用も勤めた。やがて、18世紀後半には呉服、両替の店14軒を三都に構える繁栄振りであった。