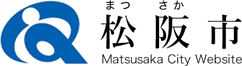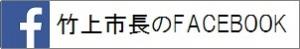本文
令和7年度当初予算提案説明における基本的な考え方について
令和7年2月定例会におきまして、令和7年度当初予算を提案するにあたり、基本となる私の考え方を述べさせていただきます。
昨年は、多くの自然災害が発生した一年でした。
元日に発生した能登半島地震では、多くの尊い命が失われ、さらに9月には、同じ能登地域を豪雨災害が襲うという悲劇がありました。
また8月には、日向灘での地震発生を受け、気象庁から初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。
さらに、本市においても、8月末に台風10号の影響を受けて豪雨に見舞われ、8月31日には線状降水帯の発生により阪内川が氾濫の危機に直面したため、流域の約1万6千世帯に対し、初めてレベル5である「緊急安全確保」を発令しました。この豪雨により、堀坂川では堤防が被災するなど、市内各所で被害が発生しました。
このような一連の災害の経験から、市民の皆様の安全と生活を守るために、自然災害対策の重要性を改めて認識した一年となりました。
一方で、三重県宝塚一号墳出土埴輪が国宝に指定されたことは、本市にとって大きな喜びであり、地域の文化的な誇りを一層高めることになりました。また、パリオリンピック2024では松阪市出身選手が躍動し、その勇姿は多くの人々に感動を与え、地域全体に希望と勇気をもたらしました。さらに「共働き子育てしやすい街ランキング2024」においては2年連続三重県1位、全国15位となり、本市の子育て支援の充実が全国的にも評価されるなど、明るいニュースもあった一年でした。
私は市長に就任以来、「誰のため、何のため」という初心を忘れず、市政運営を行ってまいりました。この根本的な問いに常に立ち返り、市政を進めることが何よりも大切であると考えております。これまで、市民の皆様の生活をより良くするため、そして私たちの地域が持続可能な未来に向けて前進するために、多くの施策を展開してまいりました。これからも、その初心を忘れることなく、新たに策定した総合計画を軸に、着実に歩みを進めてまいります。
令和7年は、松阪市が市制施行20周年を迎える記念すべき年で、まさに20歳を迎えた成人のようなものです。この節目にあたり、市民の皆様と共に進んできた歴史を振り返りつつ、20歳、まさに青春真っただ中の若々しい情熱とエネルギーを胸に、さらに明るい未来を切り開いてまいります。
また、市民の皆様の声を大切にし、持続可能な発展をめざすための施策を充実させ、本市の魅力を市内外に発信してまいります。これにより、関係人口や交流人口の増加を図り、地域経済を活性化させるとともに、松阪市へのシビックプライドを高め、皆様と共に成長し続ける松阪市をめざす「未来発信予算」を編成いたしました。
では、ここからは、令和7年度当初予算の編成にあたってのおおまかな考え方についてご説明させていただきます。
歳出については、制度改正による児童手当支給事業費等の扶助費や人件費、物価上昇や最低賃金の引上げなどに伴う委託料等の増額、さらに、新最終処分場の整備事業費及び市民病院指定管理移行に伴う繰り出し金の増加等があるなか、子育て支援、カーボンニュートラルへの取組、公共交通支援出資などの未来に向けた投資に対して、重点プロジェクト枠で約34億円、特別枠・復活枠で約11億円(うち重点支援地方交付金約4億円)を設けて対応した結果、総額約786億円と、過去最大規模の予算を編成することとなりました。
歳入につきましては、定額減税による個人市民税の減収の影響が縮小するほか、給与所得の増加による個人市民税の増収や、家屋の新増築に伴う固定資産税の増収などを見込んでおります。
地方交付税は、地方財政計画を勘案し計上いたしました。各種譲与税、県税交付金など市税以外の一般財源については、地方財政計画や三重県の予算を参考に見込んでおります。また、臨時財政対策債は、地方財政計画により、平成13年度の制度創設以来、はじめて発行額が0円とされたことから、皆減としております。
財政調整基金につきましては、昨年度は約32億円の繰り入れでしたが、令和7年度は、19億円増の約51億円を繰り入れております。重点支援交付金事業分の約4億円については、申請した実施計画の承認後、財源の振替を行います。
以前より、「任期中の借金を増やさない」と申し上げております。
令和7年度は、臨時財政対策債の発行が0円のため、市債総額で申し上げますと、令和7年度末の市債残高の見込は約407億円であり、令和6年度を約29億円下回る見込みです。(令和4年度末464億円、令和6年度末436億円)
潤沢な財政調整基金のおかげで、最大規模の予算を編成することができましたが、今後も財政調整基金を活用しつつ年間総合予算により、収支均衡のとれた財政運営を図るよう努めてまいります。
次に、令和7年度の予算編成における主な4つの視点について申し上げます。
まず一つ目は「若者定住」です。
人口の自然減と超高齢社会は避けられない現実ではありますが、人口減少対策には長期的な取組が必要です。ここに育った子どもたちや若者たちが、自分たちのまちに住み続けたいと思うことが、次の世代へつないでいく大きな循環を生み出します。
このまちの元気や活力を保つためには、若者が地域に根付くことが大切で、若者が定住できる環境を整えることにより、地域社会の継続的な成長が可能となり、地域経済も活性化します。
若者が地域に定住するために、例えば産業用地の整備や奨学金の返済支援、まちの顔である駅周辺の賑わい創出などの事業を展開してまいります。
二つ目は「福祉社会の実現」です。
現在、65歳以上の人口は高止まりしており、今後さらに人口に占める高齢者の割合は増えることが予想されています。これに対応するため、超高齢社会を前提とした福祉社会の実現が求められます。
市民の皆様が安心して暮らせる環境を整えるために、福祉まるごと相談室の全地域への配置や地域の福祉を支えている民生委員・児童委員へのサポートを充実、地域公共交通への支援など、包括的な福祉施策を推進してまいります。
三つ目は「公民連携」です。
地方自治体における公民連携は、地域の持続可能な発展を実現するためには必要不可欠だと考えます。また、事業を再定義することにより、事業そのものの必要性だけでなく、事業の進め方や実施主体も明確化されていきます。
公民連携による多様な視点や専門知識が新しいアイデアを生み、市民が抱える問題に迅速に対応し、地域の課題解決に活用されることが求められています。
令和8年度からのコミュニティセンター化に向けた体制整備を進めるとともに、公益的活動を支援するコミュニティファンドの実現に向けた取組を始めます。また、行政書士による空き家所有者への支援など、民間の知恵と力を借りながら限られた資源を効果的に活用することにより、地域全体の生活の質の向上をめざしてまいります。
四つ目は「シビックプライド」です。
令和7年は松阪市制施行20周年記念イヤーです。これまでの20年間の歩みに感謝し、次の20年に向けて一層の努力を続けてまいります。一年を通して、市民の皆様から応募いただいた事業など、様々なイベントの開催により、市民の皆様とともに松阪市を全国に発信し、更なる発展をめざしてまいります。
市制20周年記念事業は、シビックプライドを醸成する絶好の機会と捉えています。市民の皆様にご参加いただき、事業を通じて郷土への誇りや愛、そして更なる一体感を育んでいきたいと思います。
さらに、行政の執行機関である市役所も、20年を機に新たな市民サービスの充実をめざしてまいります。
社会の変化に対応できる体制づくりが求められる中で、DXやAIの進展により、職員を膨大な事務仕事から解放し、多様化する市民ニーズに対応することが可能な市役所をめざしてまいります。言うなれば、市民お一人おひとりに寄り添う市民サービスの実現をめざしていくこととなります。そのためには、職員のコミュニケーション能力の強化は必要不可欠です。
また、効率的で透明性のある政策決定は、市民の皆様の信頼を得るために欠かせない手法だと考えます。過去のデータや実証的な研究に基づいて政策を立案し、効率的で効果的な施策を講じることにより、持続可能なまちづくりをめざしてまいります。
これにより、住みやすいまちづくりを進め、市民の皆様が誇りを持てる地域社会の実現をめざしてまいります。
以上、令和7年度の予算編成における主な4つの視点を申し上げました。
さらに、これらの前提として安全で安心なまちづくりは市政の根幹となるものです。南海トラフ巨大地震が想定されるなか、地籍調査の開始や防災対策の強化は重要な課題であります。
そのほかにも、スポーツと連動したまちづくりやカーボンニュートラルの推進など、引き続き長期的な視点で取り組んでまいります。
最後になりますが、今後も「スピード感」と「独自性」を追求しつつ、市民の皆様が「ここに住んでよかった」と思っていただけるまちづくりを進めてまいります。
今後とも、議員の皆様、市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
令和7年2月20日
松阪市長 竹上 真人