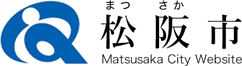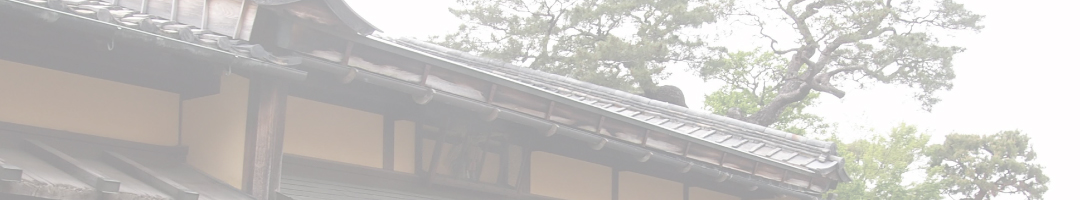本文
本居宣長稿本類並関係資料
- 本庁管内
- 市街地区
6-21
本居宣長稿本類並関係資料 附 本居宣長自画像(著色)自讃 四十四才像 並六十一才像
(もとおりのりながこうほんるいならびにかんけいしりょう つけたり もとおりのりながじがぞう(ちゃくしょく)じさん よんじゅうよんさいぞう ならびにろくじゅういっさいぞう)
国指定重要文化財
概要
- 467種1949点
- 江戸時代
- 本居宣長記念館(本居弥生氏寄贈)
- 昭和43年4月25日 追加指定:昭和54年6月6日・平成13年6月22日
国学者本居宣長(1730~1801)の72年間の生涯の資料を網羅(もうら)する。大別すると、宣長自筆資料(これはさらに著書と記録類に分かれる)、旧蔵書、記録類宣長宛書簡、そして宣長の自画像となる。以下、代表的なものを挙げてみる。
〈著書〉 『古事記伝』は35年の歳月を費やした代表作である。草稿22冊、再稿本44冊。また宣長の使用した『古事記』もともに指定されている。『源氏物語玉(たま)の小櫛(おぐし)』は源氏物語研究史に一線を画した本であり、またもののあわれ論を基調とする文学論は、近代に至るまで大きな影響力を持った。
〈記録〉 『日記』は在京中のものをふくめると10冊ある。日記とは言うものの、自分の誕生前後の事から筆を起こしている特異なものである。この他、旅に出た時の日記や、来訪者の覚え、医者としての記録である『済世録(さいせいろく)』10冊などたくさんの記録が残っている。また宣長が家族に宛てた書簡も含まれる。これらによって、宣長の生涯のみならず、当時の学者の日常生活をつぶさに知ることができる。
〈宣長宛書簡〉 家族、知人、門人の書簡が数多く残るが、白眉(はくび)は京都に遊学していた宣長に宛てた母の66通の書簡である。家長として立てながらも家名を汚さぬよう、健康を気づかい、節約を勧め、時には酒のことまで事あるごとに注意を与えている。子を思う母の気持ちもさることながら、その手紙を大事に残した宣長の人間性にも心打たれるものがある。
〈自画像〉 宣長は44歳と61歳の時、自分の姿を描いている。髪型、構図は異なるが、ともに鈴屋衣(すずのやころも)を着、桜の歌を賛としている。写真は61歳像。長身痩躯(そうく)、穏やかであったというその人柄を髣髴させる画像である。歌は「しき嶋のやまと心を人とはば朝日ににほふ山さくら花」。