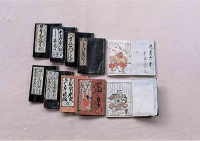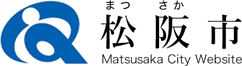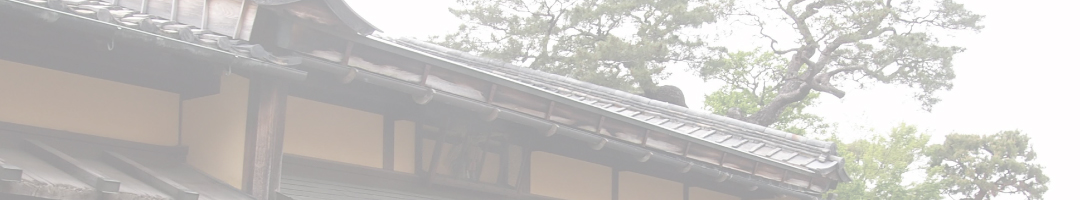ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
近世初期上方子供絵本 附 実用書 瓦版 紙袋 反古紙 絵巻写
- 本庁管内
- 南部地区
62-122
近世初期上方子供絵本 附 実用書2冊 瓦版1枚 紙袋2点 反古紙一括189枚 絵巻写1巻
(きんせいしょきかみがたこどもえほん つけたり じつようしょにさつ かわらばんいちまい かみぶくろにてん ほごしいっかつひゃくはちじゅうきゅうまい えまきうつしいっかん)
県指定有形文化財
概要
- 10冊附195点
- 江戸時代(17世紀)
- 射和町自治会
- 平成3年3月26日
延宝(えんぽう)6年(1678)、射和の商人「帯屋次郎吉」が「長九郎」という名の子を亡くし、その子の追善のために、長九郎の身の回りの絵本や手習いの反古紙類を紙袋に入れて大日堂地蔵菩薩坐像の胎内に納入したものが、そのまま現在に伝来した。なかでも子供絵本10冊は「天狗そろへ」「どうけゑつくし」「軍舞」「牛若千人切はし弁慶」「源よしつね高名そろへ」「弁慶誕生記」「おぐり判官てるて物語」等と題簽(だいせん)があり、寛文(かんぶん)期から延宝期に京都で出版された小本(タテ12cm余、ヨコ9cm余)で、現存するこの種のものでは日本最古の上方絵本であるといわれている。