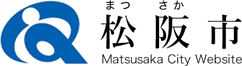本文
国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者は住民票上の世帯主です
世帯主になっている方は、勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば納税義務者になります(擬制世帯主といいます)。
擬制世帯主の所得金額に対して、国民健康保険税が課税されることはありませんが、所得に応じて適用される7割・5割・2割軽減については、加入者と擬制世帯主の所得をあわせて判定されます。
住民票の世帯主を変更した場合、当月分から新しい世帯主が納税義務者になり、前月分までは旧世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税の内訳について
基礎課税額(医療給付費分)
- 国民健康保険の運営に要する財源となります。
- 国民健康保険に加入されている方全員に計算されます。
後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)
- 後期高齢者医療制度の運営に要する財源となります。
- 国民健康保険に加入されている方全員に計算されます。
介護納付金課税額(介護納付金分)
- 介護保険の運営に要する財源となります。
- 国民健康保険に加入されている方のうち介護保険の第2号被保険者となる40歳~64歳までの方に計算されます。
国民健康保険税(所得割)の計算対象となる所得
所得割の計算には、年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得が対象となり、原則として住民税の総所得金額等が用いられています。計算対象となる所得は次のとおりです。
- 事業所得(営業等、農業)
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 公的年金やその他の雑所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 総合課税の長期譲渡所得(総所得金額に算入される金額)
- 一時所得(総所得金額に算入される金額)
- 分離課税の土地等の譲渡所得(特別控除後)
- 申告分離の上場配当所得
- 分離課税の株式等にかかる譲渡所得
- 分離課税の先物取引にかかる譲渡所得
- 山林所得
住民税との取扱いの違い
国民健康保険税の計算では住民税の総所得金額等が用いられますが、取扱いが異なる点がありますのでご注意ください。
- 退職所得は含みません。
- 分離課税の所得は特別控除後の金額です。
- 繰越雑損失がある場合は控除前の金額になります。
所得計算の概要
- 給与所得=給与収入金額-給与所得控除
※公的年金の所得がある場合は、所得金額調整控除にご注意ください。 - 年金所得(雑所得)=公的年金等収入金額-公的年金等控除
※遺族年金、障害年金等の非課税になる年金収入は含みません。 - 事業所得(※1)=事業収入金額-必要経費(※2)
※1 事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。
※2 青色事業専従者給与額は必要経費へ算入されます。 - 土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除
「配当所得」及び「株式の譲渡所得」について
上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得については、課税が清算され申告不要となっていますが、確定申告や市民税申告に計上した場合は国民健康保険税の算定に含まれます。
申告時には、所得税や市民税の還付または減額だけでなく、国民健康保険加入者の方の増額される国民健康保険税額をお考えいただきますようお願いします。
年齢による国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の該当
| 年齢 |
該当する保険制度 |
|---|---|
| 39歳まで | 国民健康保険(医療給付費分・後期高齢者支援金分) |
| 40歳から64歳まで | 国民健康保険(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分) |
| 65歳から74歳まで |
国民健康保険(医療給付費分・後期高齢者支援金分) |
| 75歳以上 |
後期高齢者医療制度 |
※それぞれ加入月数により月割で保険税(料)を計算します。