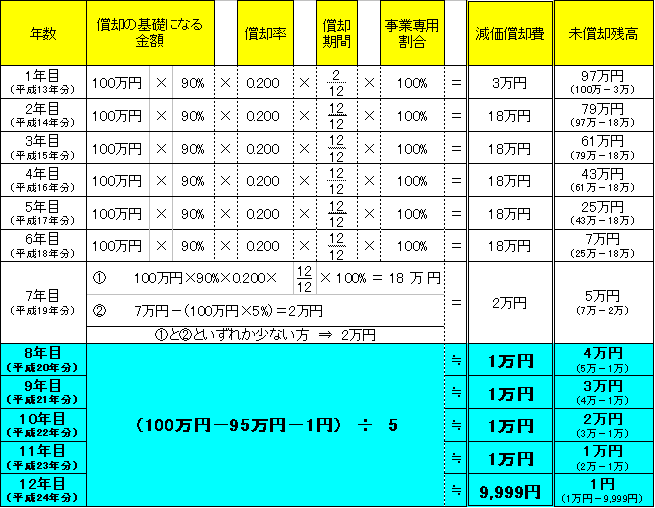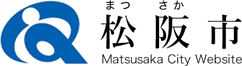本文
平成21年度課税分から適用される主な税制改正について
平成20年度以前の税制改正のうち、平成21年度課税分から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。
個人住民税における寄附金税制の拡充
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
都道府県や市区町村に対する寄附金で、5千円を超える部分について、所得割額の概ね1割を限度として所得税と合わせて控除とするものです。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
|
控除方式 |
所得控除方式 | 税額控除方式 |
|
控除額の計算式 |
「寄附金-10万円」 を総所得金額等の合計から所得控除 |
次の(1)と(2)の合計額を税額控除
|
|
控除対象限度額 |
総所得金額等の25% |
総所得金額等の30% |
個人住民税の公的年金からの特別徴収について
今後の高齢社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されているところであり、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度を導入するものです。
実施時期
平成21年10月より実施
対象者
当該年の4月1日(基準日)において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の者
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象外となります。
- 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者
- 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない者
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える者
特別徴収の対象年金
老齢基礎年金等
特別徴収の対象となる税額
公的年金等に係る所得に係る所得割額と均等割額
特別徴収を開始する年度における徴収
特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、年度前半に普通徴収、年度後半の年金支給月(10月、12月、2月)に特別徴収を実施します。
| 普通徴収 | 特別徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 税額 | 年税額の 1/4 |
同左 | 年税額の 1/6 |
同左 | 同左 |
- 年度前半において年税額の1/4ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収
- 年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
特別徴収の時期・対象税額
- 年度前半の年金支給月(4月、6月、8月)に、前年度後半の特別徴収税額の3分の1ずつを仮徴収します。
- 年度後半の年金支給月(10月、12月、2月)に、年税額から当該年度前半の特別徴収税額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。
| 特別徴収 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 税額 | 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の 1/3 |
同左 | 同左 | 年税額から仮徴収した 額を控除した額の 1/3 |
同左 | 同左 |
- 4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の廃止及び損益通算の範囲の拡大について
注)下記の赤字部分は、平成22年度税制改正より変更され、従来の軽減税率の特例が延長されます。
詳しくは平成22年度税制改正をご覧ください。
上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率は、平成16年より軽減税率10%(所得税7% 住民税3%)が適用されてきましたが、平成20年12月31日をもって廃止されます。平成21年以降は原則20%(所得税15% 住民税5%)になります。
ただし、平成21、22年分の2年間(平成22、23年度)は、下記の特例措置が適用されます。
【特例措置】(平成22、23年度に適用)
上場株式等の配当⇒100万円以下の配当について、特例措置(所得税7% 住民税3%)を適用
上場株式等の譲渡益⇒500万円以下の譲渡益について、特例措置(所得税7% 住民税3%)を適用
【損益通算】(平成22年度以降から適用)
上場株式等の譲渡損失と、配当との間の損益通算の仕組みが導入されます。
申告による方法⇒申告による方法は、所得税は平成21年分から、住民税は平成22年度分から適用されます。
特定口座を活用する方法⇒所得税・住民税とも平成22年1月から適用されます。
減価償却費の計算方法の改正について
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点において1円まで償却可能となりました。
減価償却費の計算方法
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、各年分において前年末までの減価償却費の累計額が償却可能額(取得価額の95%に相当する額)に達している場合、その達した年分以後において、次の算式により計算した金額を減価償却費として償却を行い、1円まで償却することとされました。平成21年度より適用となります。
(取得価額-取得価額の95%相当額-1円)÷5=減価償却費
(計算例)
平成13年11月に耐用年数が5年(償却率0.200)の田植機(新品)を100万円で購入した場合