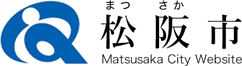本文
予防接種(子ども):HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン(目次)
健康ムービー 「未来を守るために ~受けよう!子宮頸がんワクチン~」
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンとは
HPVワクチンについて
- ヒトパピローマウイルス(HPV)には、200種類以上の型があります。その中で、HPVワクチンはがんを引き起こす可能性がある「高リスク型」に対して予防効果を持ちます。
- HPVワクチンの種類、接種スケジュールなど詳しくはHPVワクチンについてをご覧ください。
- また、さらに詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページ、ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク)をご覧ください。
- なお、このワクチンの接種をしたとしても、20歳を過ぎたら2年に1度は子宮頸がん検診を受けることが大切です。
子宮頸がんについて
- 子宮頸がんは、子宮の頸部という出口に近い部分にできるがんで、おもにヒトパピローマウイルス(HPV)に感染することによって生じます。HPVに感染しても、すぐにがんになるわけではなく、ほとんどの場合は自然に消えますが、一部が子宮頸がんへと発展します。
- 日本では毎年、約1万人の女性がかかるがんで、さらに毎年、約2,700人の女性が亡くなっています。近年では若い女性の子宮頸がんり患が増えています。
定期接種について
対象年齢について
- 小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女性です。標準的な接種年齢は中学1年生の女性となっております。
接種期間について
- 高校1年生相当の年度の年度末(3月31日)です。
接種方法について
- HPVワクチン接種の受け方をご覧ください。
令和7年4月からの経過措置(接種期間延長)について
対象者について
下記すべてに当てはまる方
- 平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性
- 令和4年4月1日~令和7年3月31日の期間中にHPVワクチンを1回以上接種し、2回または3回の接種が完了していない方
- 接種時点で松阪市に住民登録がある方
ご自身が対象か迷う場合はHPVワクチン令和7年度の経過措置対象者チェック [PDFファイル/241KB]もご覧ください。
経過措置(接種期間延長)の期間について
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
接種方法について
- これまでと予診票、接種方法は変わりません。
- 詳しくはHPVワクチン接種の受け方をご覧ください。
経過措置が実施された経緯(参考)
- 令和6年夏以降のHPVワクチンの大幅な需要増加により、接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月31日までに接種を開始した方が全3回の接種を公費で完了できるように、1年間の経過措置が設けられました。
- 詳しくは厚生労働省のホームページヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク)をご覧ください。
HPVワクチン接種の受け方
接種回数について
- 小学6年生~高校1年生相当の方は合計2回または3回接種します。接種回数と接種間隔はワクチンの種類によって異なります。
- 高校2年生相当以上の年齢の方は合計3回接種します。既に1回接種された方は残りの2回、2回接種された方は残りの1回となります。
- 1回目、2回目に気になる症状が現れた場合は、以降の接種をやめることも出来ます。
- 接種回数と接種間隔について詳しくはHPVワクチンについてをご覧ください。
接種方法について
- 県内の協力医療機関で予防接種を行います。松阪市、多気郡3町の協力医療機関については予防接種協力医療機関についてをご覧ください。
- 医療機関で予防接種を受ける前に必ず電話等で予約をしてから接種を受けてください。
- 接種当日の持ち物は予診票、母子健康手帳、マイナンバーカードなどの住所が確認できるものです。予診票を紛失された方は接種当日までに予診票発行申請を行ってください。予診票発行申請については予診票について(発行申請フォーム)をご覧ください。
接種費用について
- 無料です。
HPVワクチンについて
効果について
- ヒトパピローマウイルス(HPV)には、200種類以上の型があります。その中で、HPVワクチンはがんを引き起こす可能性がある「高リスク型」に対して予防効果を持ちます。
ワクチンの種類について
- サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)の3種類あります。シルガード9(9価)は令和5年4月より新しくキャッチアップ接種のワクチンとして用いることができるようになりました。
- それぞれのワクチンで予防できるHPVの型が次のとおり異なります。
| ワクチンの種類 | 16/18型 | 6/11型 | 31/33/45/52/58型 |
|---|---|---|---|
| シルガード9(9価) | ○ | ○ | ○ |
| ガーダシル(4価) | ○ | ○ | |
| サーバリックス(2価) | ○ |
- 16型、18型の免疫により子宮頸がんの原因の50%~70%を防ぎます。
- さらに31型、33型、45型、52型、58型を加えると80%~90%を占めます。
- 6型、11型は性器にイボを起こす尖圭(せんけい)コンジローマの原因といわれ、それに対する予防となります。
リスク(副反応)について
- 主な副反応は接種部位の痛み、腫れ、赤みや発熱ですが、その多くは一過性で回復しています。
- 非常にまれですが、重い副反応として、呼吸困難やじんましん等(アナフィラキシー)、手足の力が入りにくい(ギランバレー症候群)、頭痛・嘔吐・意識低下(ADEM)等があります。
健康被害救済制度
- 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じ、国の審査会で予防接種によるものと認定された場合には予防接種法に基づく給付を受けることができます。
標準的な接種スケジュールについて
接種するワクチンの種類によって異なります。
| ワクチンの種類 |
1回目から |
1回目から |
回数 |
|---|---|---|---|
|
シルガード9(9価) |
6か月 | ― | 計2回※ |
|
シルガード9(9価) |
2か月 | 6か月 | 計3回 |
| ガーダシル(4価) | 2か月 | 6か月 | 計3回 |
| サーバリックス(2価) | 1か月 | 6か月 | 計3回 |
※シルガード9(9価)を用いて1回目を15歳になるまでに受けた場合、2回で接種を完了とできますが、2回目の接種が1回目から5か月に満たない場合は3回接種します。また、シルガード9(9価)ワクチンを用いて1回目を15歳になるまでに受ける場合でも3回接種とすることも可能です。
標準的な接種スケジュールをとることができない場合
| ワクチンの種類 | 標準的な接種スケジュールをとることができない場合 |
|---|---|
| シルガード9(9価) | 2回目は1回目から1か月以上の間隔をおく。3回目は2回目から3か月以上の間隔をおく |
| ガーダシル(4価) | 2回目は1回目から1か月以上の間隔をおく。3回目は2回目から3か月以上の間隔をおく |
| サーバリックス(2価) | 2回目は1回目から1か月以上の間隔をおく。3回目は1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上の間隔をおく |
接種間隔について詳細はHPV ワクチンの接種間隔について [PDFファイル/310KB]をご覧ください。
県外の医療機関での接種を希望される方へ
- 三重県外の医療機関で予防接種を受けられる場合は事前に申請してください。
- 詳しくは県外で予防接種を希望する場合(子どもの定期接種)をご覧ください。
予診票について(発行申請フォーム)
- 定期接種の方は中学1年生の女子の保護者に年度初めに個別に郵送をします。
- 松阪市に転入された方、予診票を紛失した方、予診票が届いていないが接種を希望する方は次のいずれかの方法で予診票の発行申請をしてください。
インターネットからの申請
- こちらの申請フォームから申請してください。
- 申請には母子健康手帳(予防接種の記録が分かる部分)の画像(写真)アップロードが必要です。万が一紛失してお持ちでない場合はこの限りではありません。
- 健康づくり課から、HPVワクチン予診票をご住所へ郵送します。
- 届くのに目安として1週間程度かかります。お急ぎの場合は窓口での申請を行ってください。
窓口での申請
申請場所
| 申請場所 | 住所 | 電話、FAX番号 |
|---|---|---|
| 健康づくり課 (松阪市健康センターはるる) |
三重県松阪市春日町一丁目19番地 | 電話(0598)31-1212 FAX(0598)26-0201 |
| 嬉野保健センター | 三重県松阪市嬉野町1434番地 | 電話(0598)48-3812 FAX(0598)42-4945 |
| 飯南地域振興局地域住民課 | 三重県松阪市飯南町粥見3950番地 | 電話(0598)32-8020 FAX(0598)32-3771 |
| 飯高地域振興局地域住民課 | 三重県松阪市飯高町宮前180番地 | 電話(0598)46-7112 FAX(0598)46-1092 |
持ち物
- 母子健康手帳
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
郵送での申請
- HPVワクチン予診票発行申請書 [PDFファイル/175KB]と母子健康手帳(予防接種の記録が分かる部分)のコピーを健康づくり課(松阪市健康センターはるる)(〒515-0078 三重県松阪市春日町一丁目19番地)へ提出してください。
- HPVワクチン予診票をご住所へ郵送します。
予防接種協力医療機関について
令和7年度 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 協力医療機関 [PDFファイル/360KB]
積極的な勧奨の差し控えと再開の経緯について
- HPVワクチンは、平成25年から定期の予防接種に位置づけられましたが、平成25年6月に行われた厚生労働省の検討会でワクチンとの因果関係は不明ながら、持続的な痛みを訴える重篤な副反応が報告されていることから、一時的に積極的な勧奨を差し控えておりました。
- その後、国で継続的に議論が行われ、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことにより、令和3年11月26日に発出された通知にて、積極的勧奨を差し控えている状態については、終了させることとなりました。
- 積極的勧奨を再開することになりましたが、HPVワクチンの接種は強制ではありません。ワクチンの効果と副反応のリスクを十分に理解した上でご判断いただきますよう、お願いいたします。
ダウンロードファイル
小学6年生~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) [PDFファイル/2.72MB]
小学6年生~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) [PDFファイル/3.58MB]
健康ムービー 「未来を守るために ~受けよう!子宮頸がんワクチン~」
監修・出演:イワサ小児科 院長・松阪地区医師会 感染症担当理事 岩佐 正さん
健康ムービーについて、詳しくは「松阪市 「健康ムービー」 中学生のみなさんへ ~未来のあなたのために“今”できること~」のページをご覧ください。