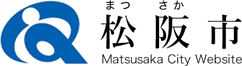本文
平成20年度課税分から適用される主な税制改正について
個人市民税と個人県民税をあわせて、一般的に個人住民税と呼ばれています。以下「住民税」と標記します。
平成19年度以前の税制改正のうち、平成20年度課税分から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。
住民税の住宅借入金等特別税額控除の創設 (平成20~28年度)
所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方(平成18年12月31日までの入居者に限ります。)について、税源移譲に伴う税率変更により平成19年分以降の所得税額が減少したため同控除が所得税から控除しきれなくなった場合の対応措置として、税源移譲前の所得税額において控除できた額と同等の負担となるように、翌年度(平成20年度以降)の住民税から減額する措置が創設されました。
なお、平成20年度以降この適用を受けるためには、対象となる年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、その年の1月1日現在お住まいの市町村長へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただく必要があります。
| 住民税の住宅借入金等特別税額控除額 | = |
(ア) (イ)のうちいずれか少ない方の金額 |
- | 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除前) |
関連書類
住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告をされない方用)
住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告をされる方用)
申告と提出先
- 給与収入のみを有しており確定申告を提出しない納税義務者
年末調整において所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で確定申告をされない方は、勤務先より交付される源泉徴収票(原本)を添付して、3月15日(平成20年は3月17日)までに「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税義務者用)」をその年の1月1日現在お住まいの市町村へ提出してください。 - 確定申告書を提出する納税義務者
確定申告時に「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税義務者用)」を確定申告書とともに税務署へ提出してください。
年度間の所得変動に係る経過措置(平成20年度のみ)
税源移譲に伴う住民税と所得税の税率変更により、平成19年度住民税(平成18年中の所得等に基づき計算)が増額となった場合は、平成19年分所得税(平成19年中の所得等に基づき計算)が減額となるため、「住民税+所得税」の負担額は極力変わらないようになっています。
しかし、平成19年中の所得が無くなった方や所得税が課税されない程度まで所得が減少し一定の要件に該当する方は、住民税の増額のみが発生するため、その救済措置として、平成19年度住民税を減額する経過措置が設けられました。この措置により、平成19年度住民税の納付済額が当該減額後の額を超える場合は還付となります。
なお、この適用を受けるためには、平成20年7月1日から7月31日までの間に、平成19年1月1日現在お住まいの市町村長へ「平成19年度分住民税減額申告書」を提出していただく必要があります。
【対象者】 次の(1)と(2)の条件の両方を満たす方
| (1) | 平成19年度住民税の合計課税所得金額 (申告分離課税分を除く) |
> | 所得税との人的控除額の差の合計額 |
|---|---|---|---|
| (2) | 平成20年度住民税の合計課税所得金額 (申告分離課税分を含む) |
≦ | 所得税との人的控除額の差の合計額 |
※平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転居されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、対象となりません。
| 平成19年度住民税額から差し引く額 | = | 平成19年度住民税額 (税源移譲後の税率にて計算(調整控除適用)した税額) |
- | 平成19年度住民税額 (税源移譲前の税率にて計算した税額) |
関連書類
平成19年度分住民税減額申告書
関連リンク先
総務省・全国地方税務協議会の作成によるリーフレット
なお、具体的な申告手続きについては、詳細が決まり次第、お知らせいたします。
地震保険料控除の創設
従来からの損害保険料控除が見直され、新たに地震保険料控除が創設されました。
なお、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等については、これまでの損害保険料控除を適用することができます。(短期損害保険料控除は廃止されました。)
地震保険料控除の内容
- (ア)地震保険料の控除額…地震保険契約に係る地震等相当分保険料×2分の1(最高25,000円)
- (イ)長期損害保険料の控除額…下表のとおり
| 支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 5,000円超15,000円以下 | 支払保険料×2分の1+2,500円 |
| 15,000円超 | 10,000円 |
(ウ)上記(ア)(イ)の両方を適用する場合は、それぞれの控除額を合わせて25,000円が上限となります。
減価償却制度の改正
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点において1円まで償却可能となりました。
| ・平成19年4月1日以後に取得したもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (現行) | 償却費の額 | = | (取得価額-残存価額) | × | 定額法の償却率 |
| (改正後) | 償却費の額 | = | 取得価額 | × | 定額法の償却率 |
| ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの | |||||
| 現行のとおり(平成21年度から一部改正あり) | |||||
なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、従前のとおりです。ただし、既に償却可能限度額まで達している場合にあっては、平成21年度以降の住民税から一部改正があります。