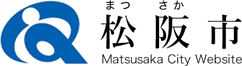本文
地籍調査
地籍調査の概要
地籍調査とは
『地籍』とは、『土地の戸籍』のことです。
その土地がどこ・どれだけの面積があるのか・どのような形なのか・どのように使われているか、といったことを指しています。
現在、この地籍に関する情報は法務局に登記簿・公図という形で保存されています。
しかし明治時代に作成されたものが多く、土地の境界が不明確、現況にそぐわないといった箇所が多く出てきています。
『地籍調査』とは、土地所有者のみなさまのご協力のもと、一筆ごとの土地について、土地境界をはじめとした土地情報について調査・確認し、現代の精密な測量技術により測量することで、地籍の明確化を図るために行われるものです。
地籍調査をしていないと、次のような心配があります
相続した土地がわからない
相続を受けた土地の正確な位置がよくわからなかったり、隣地との境界争いになることがあります。
土地取引が円滑にできない
土地を売買する際、隣地との境界確認に時間がかかったり、また、登記簿上の面積と実測面積が異なっているとトラブルの原因となり、土地取引が円滑にできないことがあります。
公共事業が進まない
道路、河川、土地改良などの公共事業を実施する際、現地と登記の内容が一致していない場合があるので、計画策定、設計、用地買収のための各種調整に時間を要し、事業の進行の妨げになることがあります。
災害などの復旧に時間がかかる
地震、土砂崩れ、水害などの災害が起きた場合、災害前の土地の境界が確認できない場合があり、早期に復旧をしようとしても、境界確認などに時間を費やし、なかなか復旧工事にかかれない場合があります。
まちづくりの計画が立てられない
地籍調査をしていないと、用地取得が可能なのかどうかわからないため、計画がたてられないことがあります。
地籍調査はこんなことに役立ちます
境界争いなど土地に関するトラブルの未然防止に役立ちます。
土地登記簿に正確な土地の情報が反映されるため、次世代へ安心して土地を引き継げることになります。また、土地の売買する際にも円滑に進めることができるようになります。
地震・土砂崩れ・水害などの災害が起きた場合でも、座標により境界を復元することができるため、その後の復旧活動に迅速に取り掛かることが可能となります。
各種公共事業の計画・設計・用地取得するにあたり、事業の効率化と費用の削減に役立ちます。
土地の面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。
地籍調査の流れ
●地籍調査に必要な経費の住民負担はありません
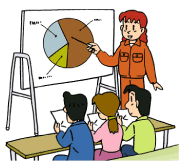

【1】説明会の実施 【2】現地立会
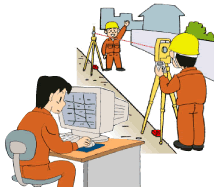
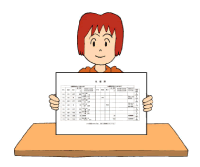
【3】地籍測量 【4】地籍簿作成
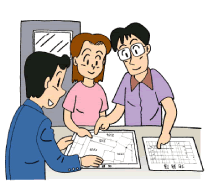

【5】閲覧 【6】登記所へ送付
出典:地籍調査Webサイト (https://www.chiseki.go.jp/about/flow/index.html)
みなさまへお願い
- 地籍調査は、複数年かけて一つの地区を調査します。順を追って各地区を調査していきますので、調査対象となりましたら、調査へのご協力をよろしくお願いいたします。
- 立会して決めた境界をもとに測量した結果、土地の実測面積は登記面積に対して差が生じることがあります。
- 隣接する土地との境界が決まらないときは、測量ができませんので、「筆界未定(ひつかいみてい)」という処理をいたします。筆界未定の場合は、地籍図に境界線が表示されません。
- 筆界未定の土地について、今後土地の境界確認が必要となったとき、測量などの費用はすべて土地所有者個人の負担となります。