松阪路~伊勢街道・初瀬街道~
伊勢街道沿い・初瀬街道沿いを歩く
伊勢街道は、日永(四日市市)の追加分で東海道と分岐して、伊勢湾沿いを山田(伊勢市)へと向かうおよそ十八里の道。日永の追分、津、松阪、斎宮(明和町)を経て山田(伊勢市)へ向かう街道は、幕府によって脇街道として整備され近世の形になった。
また、初瀬街道は、初瀬・榛原を経て、宇陀川沿いに伊賀盆地に出て、青山峠を越え、津市を通り六軒(松阪市)で伊勢街道と合流する。
1 松浦武四郎誕生地 2 松浦武四郎記念館


松浦武四郎は、幕末に6回の蝦夷地調査を行い、膨大な記録を残し、詳細な地図を出版した他、明治維新期に「北海道の名付け親」となった人物。松浦武四郎記念館では、重要文化財に指定された1505点の資料を中心に、充実した映像コーナーや武四郎クイズなどで武四郎を紹介している。
3 格子戸のまち並み(市場庄町)

格子戸が付けられた妻入町家や土蔵が軒を連ね、街道が大変にぎわった当時の面影を残している。
4 屋号の看板

「ぞうりや」や「かご大」、「合羽屋」など、名前だけで、商売がわかる屋号。昔から使われている屋号の看板をそれぞれの家に取り付けている。
5 三井家発祥地

本町通の白い塀に囲まれたこの地は、三井家の基礎を築いた三井高利が生まれ育った場所。(市指定史跡)〈内部は非公開〉
6 旧小津清左衛門家

江戸で一番の紙問屋、豪商・小津清左衛門家の邸宅を資料館として公開。格子と矢来のある質素な外観からすると意外なほど広い屋敷内には、2つの土蔵も残る。展示品の中には「千両箱」ならぬ「万両箱」もあり、「江戸店持ち伊勢商人」の暮らしぶりが偲ばれる。(県指定有形文化財)(市指定史跡)
7 旧長谷川治郎兵衛家

魚町通りにあるこの邸宅は、江戸時代の木綿問屋「丹波屋」。格子、霧よけ、5つの蔵、そして、うだつの上がった屋根など落ち着いたたたずまいの中に当時の松阪商人の隆盛ぶりがうかがえる。(国指定重要文化財)(県指定史跡及び名勝)
8 松阪もめん手織りセンター

三井家の跡地にあり、中では昔ながらの機織り機が軽やかな音色を響かせる。また予約をすれば機織り体験(有料)ができる。松阪もめんの洋服、着物、小物なども販売。
9 豪商のまち松阪観光交流センター

松阪の歴史や文化、食などの情報を魅力たっぷりに発信する、松阪観光の拠点。1階では、お土産や観光情報収集、2階では、松阪の歴史を展示やシアターで学べる。

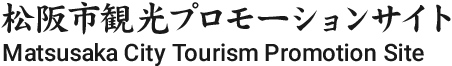






 松阪市
松阪市